東京・両国の旧安田庭園の一角に佇む刀剣博物館。同館は日本美術刀剣保存協会によって運営されており、2017年に現在の地に移転してからも、美術工芸品としての日本刀の魅力を発信し続けている。今回は同館の学芸員、荒川史人さんに話を伺った。

近年は外国人観光客の来館が多く、平日では来館者の約半分を占めているという刀剣博物館。同館では通常の展示に加えて、定期的に展覧会や初心者へ向けた刀剣鑑賞のマナー講座などさまざまなイベントを実施している。来館者からは、同館の展示を通して初めて刀剣の見方を学ぶことができたという声もある。今まで実施した展覧会の中で特に好評だったのは、江戸時代後期から幕末にかけての作品を中心とした「江戸三作」展だ。普段見ることができない作品は人気が高く、同館が両国に移転してから過去最高の来館者数だったという。
荒川さんは日本刀の魅力について「同じ作品が一つもなく、実際に手に取って見ることができること」だと語る。他の美術品と違い、日本刀は手に取って鑑賞することが可能だ。同館でもイベントを通して刀剣に触れる機会を提供しており、魅力をより近くで感じることができる。
では、若い世代へと日本刀文化を継承していくために、博物館はどのような役割を果たしているのだろうか。一般的に博物館では保存と展示・普及の両立が求められる。美術品を長期保存することのみが目的であれば、展示を行わないほうが良い。しかし、それでは将来的に価値の分かる人がいなくなってしまう。同館は刀剣の展示を通して、その価値を広く認知してもらう役割を担っている。
最後に荒川さんは「刀剣を制作する側と愛好する側への両方の支援が私たちの務めであり目的だ」と語った。これからも同館は、刀剣に関わる職人が持つ技術の伝承支援に加え、刀剣を鑑賞する人たちへ魅力の発信も行っていく。また、日本刀文化をより広めるため、今後は需要に応じて展示解説の多言語化などにも取り組みたいという。刀剣に興味がある人は、ぜひ刀剣博物館に足を運んで、その魅力を間近で感じてほしい。
(橋本こと乃)
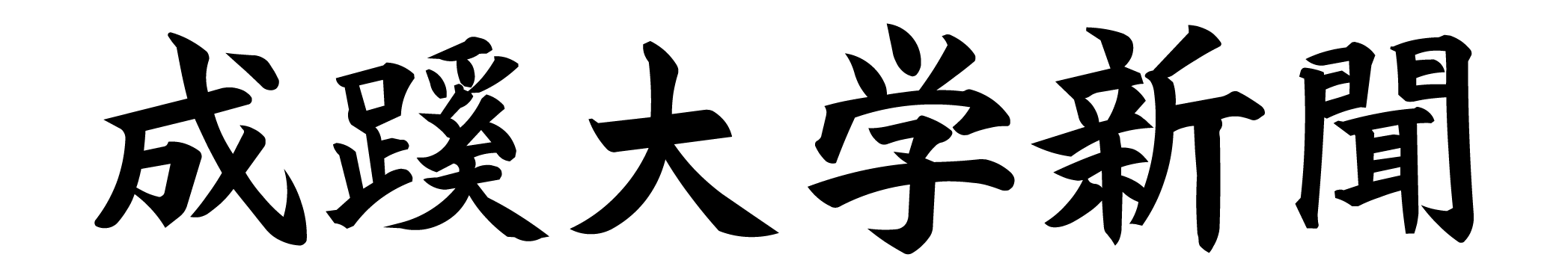



コメント