5年~10年という長い修業期間を経て、美術工芸品である日本刀を手がける刀鍛冶。刀づくりは、完成するまでに数多くの工程と長い時間を要し、その過程には緻密で高い技術と集中力、そして何よりも刀鍛冶としての精神力が求められる。では実際に、刀鍛冶はどのような想いを持って刀づくりに向き合っているのだろうか。今回は全日本刀匠会で副会長を務める久保善博さんにお話を伺った。
久保さんは資格を取得して30年を過ぎる刀鍛冶で、映りを再現した長光の作風と、自分で砂鉄や鉄鉱石から玉鋼を作る、たたら製鉄を得意としている。久保さんが副会長を務める全日本刀匠会では、後継者の育成支援や展覧会の開催を行っている。将来的には海外でも展覧会を開き、海外の人にも日本刀の魅力を伝えたいという。
久保さんは刀鍛冶であると同時に、研究者としての一面も持っている。久保さんが一昨年執筆した論文では、たたら製鉄において砂鉄の中に含まれる酸化チタンが非常に重要な働きをしていることを世界で初めて証明。その功績が認められ、日本鉄鋼協会の俵論文賞を受賞した。久保さんは過去の国宝クラスの名刀のような、「切れるのは当然だが、本当に美しい刀」が理想の刀だと話す。「この理想を実現させるために、これからも研究を続けていくが、満足いくことなく刀鍛冶人生を終えると思っている」とも語った。その終わりなき追究が、久保さんの職人としての原動力になっている。
刀鍛冶が心を込めて制作した日本刀は、世界でも有数の切れ味をもつ刃物でありながら、研ぎ上がった刀身は宝石のように美しい。日本刀の機能美と芸術性が、世界中の人々の心を魅了する日も、もう間近に迫っているのではないだろうか。
(長谷川真由)
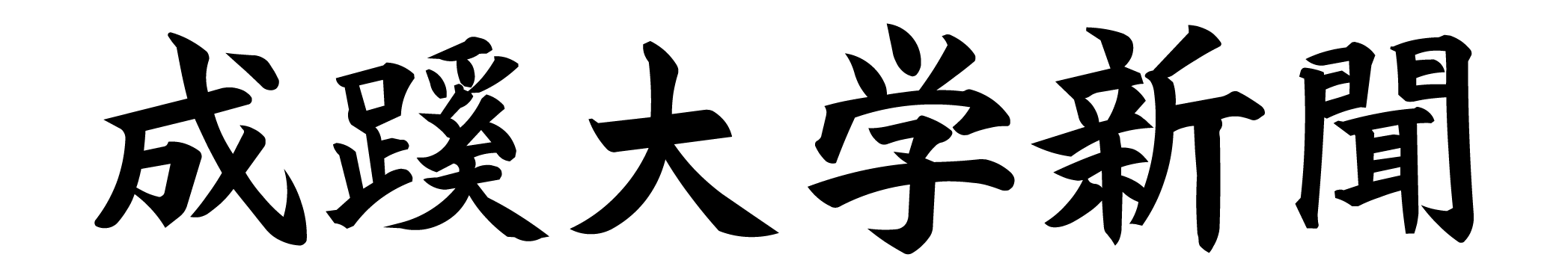



コメント