近年ブームを巻き起こしている日本刀。現代の人々はなぜそれらに魅了されるのか。今回は日本刀の魅力をその歴史という観点から探るべく、國學院大學神道文化学部神道文化学科の笹生衛教授に話を伺った。
日本に鉄の刀が渡来した弥生時代以降、刀の形状は時代と共に変化していった。古墳時代初期には刀身が真っすぐな直刀や、刀身が刃に反った「内反り」の刀が現れ、7世紀には「方頭大刀」、9世紀には柄が曲がった「湾刀」が生まれた。その後、平安時代中期に完成した、柄が曲がった形状の「毛抜形太刀」は現在の日本刀の直接の起源になったとされている。
笹生教授は、こうした変遷の背景として「社会構造や環境の変化による影響が大きい」と指摘する。9世紀後半から10世紀の平安時代中期は、古代社会が大きく変化した時代だ。全国的な戦乱が増え、治安が悪化する中で徴税が難しくなり、役人たちは自衛のために武装を始めた。加えて、血縁関係や家族が解体・分散していった時期でもあり、不安定な気候も相まって社会全体の不安が拡大した。こうした状況において、刀が戦だけでなく日常的にも使用されるようになった。弥生時代以来真っすぐだった刃が、9世紀頃以降では実用性を求めて湾曲していった。このような形状の変化は、多くの命が脅かされ、人々が武装化するようになった中世社会の情勢を反映している。
笹生教授は「日本刀は単なる武器ではない」ということを強調する。弥生・古墳時代の刀剣は東アジアの大国である中国から伝来した最先端の道具だった。そのため、古くは3世紀ごろから、鏡と並ぶ古墳の副葬品として重要視されていた。刀剣に対する信仰や神聖性は、各地の伝承や逸話を通して受け継がれていった。そのため、武器として使用される時代になってからも、人々は優れた刀に霊力を感じて神格化し、神仏へ奉納し続けた。
笹生教授は、日本刀は「日本の2000年の歴史における技術革新の結晶」であると語る。時代と共に実用品として使用されていただけでなく工芸品としても扱われ、変化を続けてきた歴史とその美しさに日本刀の価値を見出すことができるという。
日本人の精神性と美意識の象徴である日本刀。世相を反映して変化してきたその姿はまさしくその時代を映し出す鏡である。昔も今もその色とりどりの側面に人々は魅了され続けているのだ。
(増山瑠華)
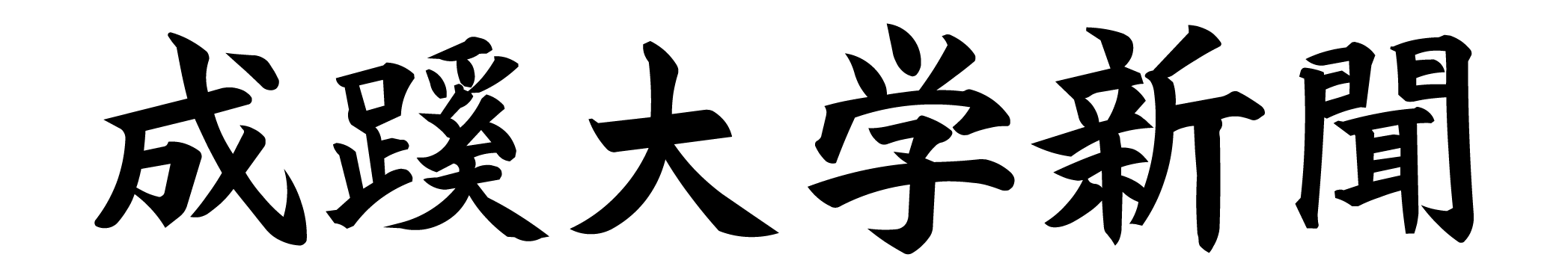



コメント